1.要約
学生時代からの友人で、古本屋『京極堂』を営む中禅寺秋彦の家を関口巽が訪ねて眩暈坂を歩くところからメインストーリーが始まる。物書きの端くれである関口が、友人の妹であり、編集会社に勤め、時折記事の寄稿を働きかけてくれる仕事上の関係もある中禅寺敦子から耳にした「二十か月もの間、子供を身籠っているという妊婦」の話について意見を聞くためだ。話の詳細を伝え、不思議だという関口に中禅寺は、この物語以降でも出てくる有名なセリフを口にする。
「この世には、不思議なことなど何もないのだよ、関口君」
古本屋の主人であると同時に憑物落としをも請け負っている中禅寺は、関口との会話の中で、人が不思議ととらえる事象に対する関係性を、脳と心の関係、無意識、潜在意識、記憶、呪いや伝承、仮想現実など、広範な知識と考察、洞察とによって説明する。そして、その流れで妖怪や言い伝えなどもまた一定の理を含んでいるという。
関口は自らが報告した妊婦の話の出所が実は雑司ヶ谷のとある医院にあることを友人の口から知る。またそこで失踪者が発生している事件も起きていること、失踪者は学生時代の二人の友人であることから、関口はやはりこれも学生時代の同僚で旧華族でもある榎木津礼二郎に会いに行くよう勧められる。容姿端麗にして破天荒な性格の榎木津は神保町で「薔薇十字探偵社」を経営する探偵だが、彼の“他人の記憶が見える”という特殊な才能?は、事件を解決するのではなく勝手に終わらせると言われている。
到着した関口を出迎えたのは使用人の安和寅吉で、間もなく依頼人が来る予定であるにもかかわらず、探偵は明け方まで友人と飲んでいたこともあってまだ隣室で眠っていた。
探偵社を訪れた女性は、久遠寺の娘である涼子だった。二十か月もの間子供を身籠り続ける妹の梗子の件ではもちろんなく、その夫である藤野牧郎、通称藤牧の失踪についてだ。依頼人の前にあらわれた榎木津は、すぐ依頼人と関口の記憶を通して二つのことを言い当てる。涼子が嘘をついているのではないかということ、つまり藤牧はすでに死んでいてそれを知っているのでははないか、ということ、もう一つは涼子と関口が互いに知り合いではないかということだ。後者について、関口はよく覚えていたが涼子は記憶にないようであった。彼女のしぐさや雰囲気には嘘をついているような感じはない。榎木津の能力は他者の記憶を通して現実が見えることであり、そこに嘘はない。
榎木津とともに“探偵”扱いされて久遠寺医院に乗り込む羽目になった関口と榎木津、そして実際を解明することを望む中禅寺敦子が見たものは、古来から連綿と家系に受け継がれたものだった。呪い、多重人格、無頭児、遺伝・・・。何重にも絡め取られ、哀しい現実から動くことができない人々に、拝み屋中禅寺秋彦=京極堂がささやく。
2.著者について
あまりに有名な方なので“省略”しようと思ったのですが、一応ふれておきます。
1963年生まれ。北海道小樽市出身。小説家として本作でデビューしたのは1994年。次作「魍魎の匣」で日本推理作家協会賞長編部門賞を受賞したのをはじめ、「嗤う伊右衛門」で泉鏡花賞、「覘き小平次」で山本周五郎賞、「後巷説百物語」で直木賞、「西巷説百物語」で柴田錬三郎賞と錚々たる受賞歴がある。また、柳田国男の遠野物語によせて著した「遠野物語remix」では、解釈を新たにした物語をうみだし、遠野文化賞をえている。
アートディレクター、日本推理作家協会理事長でもある(妖怪画家でもあったと聞いた記憶がある)。
宮部みゆき、大沢在昌とともに、株式会社大沢オフィスにより運営されている「大極宮」で、自身の作品紹介やブログでの近況報告を行っている。
妖怪について右に出る者はいないほど筋金入りの妖怪通。世界妖怪協会・世界妖怪会議評議員。
3.気づき
巷で噂になっていたから手に取ったのだが、既に「絡新婦の理」か「塗仏の宴」が出ていた頃で、京極氏はテレビやメディアに頻繁に顔を出していた。天邪鬼の私は、皆にもてはやされている作品だということもあって、いささか懐疑的にページをめくり始めたのだが、「長いな」「くどいな」などと心の中で悪態をつきながら、結局最後までのめりこむように読んでしまった記憶がある。
要約の中で、京極度が出張る後半部分をほとんど端折り、最初のシーンの説明をやや細かく取った。それが、今回触れたいことだからである。
要約でも触れた通り、記憶や脳と心の関係など、一見物語とは関係ない領域で事細かに語られていて、集約された説明としては下手な解説本や専門書を読むより整合が取れていると感じた。一番伝えたいことはそういうことだ。また、自分の心の中が人に読まれている、漏れ出してしまうと妄想する統合失調症(=精神分裂病)とはまったく別の話だが、記憶はものに宿り、共有されうるとする部分の説明は面白い。心理学はある線を一歩踏み超えるとオカルティックな領域になってしまうが、誰に話すでもなく考えていたことで自分の中ではそれなりに妥当性を感じていたことが幾ばくかの時間の経過の後、他人が同じように考えていることを、人の考えることなんて大して変わらんと言われていることは実は・・・などと「妄想」してしまう。
もっとも引き込まれたのは、脳と心の関係の部分だ。脳と心の間に意識をおき、現実と内面という全く相いれない二つの世界をつなぐ構図を京極堂に滔々と語らせるところは、著者が実はとてもこの分野に秀でているのか、単にこの部分に対する異常な興味と洞察のためなのかは知らないが、ロジャースや前野隆司氏の「脳はなぜ心を作ったか」の世界を彷彿とさせてくれた。
心理描写にすぐれた本は古今東西随分あるが、心理学的な領域をこれほどあたかもそうであるがごとく語ってくれるフィクションというのは、引き込まれてしまうものだ。推理小説なのだから論理を追うという意味では当然なのかもしれないが、それを踏まえてたとしても物語とは別の側面で面白さを感じてしまうのは、自分がこの分野に人並み以上に興味を感じているからかもしれない。
「この世には、不思議なことなど何もない」と言い放ち、伝承とか言い伝えといった、とかく古いの一言で切り捨てられてしまいがちな遺産を、を今の時代(といっても昭和の前半時代ですが)に“論理的に”組み込むとこんな物語ができるのだなあと感じ入っている。
このシリーズの登場人物たちにイメージしにくい部分があるとすれば、京極堂を除く皆が戦争帰りだということだろうか。自分がそういった方々と接した経験が乏しいからかもしれない。物語なのでキャラが立っていた方が面白いわけで、特に異論はないです。
4.おすすめ
前章で述べた通り、推理小説にして怪奇小説であるとともに、(その一部なのだが)心理小説の側面から読むと面白いです。ここではもっぱらその観点から推奨させていただきます。
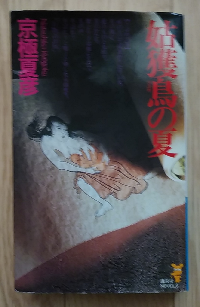

最近のコメント