1.要約
日本では思想とは現実に影響を及ぼさないものである。現実とは世間のことである。その世間もまたある種の思想である。双方とも人が見聞きし、考えたものである。つまり脳の中(での解釈)のことだからである。これらは相互に補完的である。いささか乱暴に内容を結びつけるとそう言っていることになる。
また、本来の意味における思想は日本にはないことを、丸山真男、山本七平、加藤典洋らを引用して言う。別の言い方をすると、思想がないという思想、と表現する。それらを明治維新以降、あるいは第二次大戦の敗北以降の日本の変わり身の早さを例としてあげている。
この『思想なんかないという思想』、これを日本で何とか維持するのはどうすればいいか、それを考えている。つまり、著者はこの思想=無思想を肯定している。
明治維新における和魂洋才で、和魂の実体とは世間の慣習ことだ。しかるに、西欧思想に「対抗して」和魂を思想と取り違えて雁字搦めの昭和を迎えた。世間が危うくなったわけである。
明治にそうであったようには世間は既にしっかりしておらず、「思想がない社会」で「世間という現実」がおかしくなれば、全てが崩壊に近づく。そうやって昭和の初めが訪れた。
日本の社会で自分とは「世間に作られる自分」である。これは仮初ではなく立派な本来の自分である。その世間が不安定化すれば、自分もまた不安定になる、それが今の日本で起こっていることで、それをして不安と呼んでいる。
歴史を見ると、有思想の世界では大虐殺が当たり前で問題にならない。主張する内容があるからである。この手前勝手を許してはならないなら、無思想の思想を徹底して説く必要がある。しかも、おそらく有思想で作られた言語を使って無思想を説明することが日本人の使命である。
武道、茶道など道の世界を思想として説明するのは難しい。理屈ではないからだ。だからこそ、今も禅があちこちに残っている。ただし、徐々に「言葉にならないものは存在しない」傾向が表れてきている。
思想と身体はバーターである。思想は言語の世界、身体は非言語の世界である。そしてこの二つは切り離すことができないはずのものである。しかるに純粋な思想というものは本来ありえない。
言語は意識の世界である。様々な「同じ」があることを前提に成立している。リンゴもミカンも果物、サバもアジも魚。それらは食物、さらには、と繰り返しながら世界を単純化していく。これを突き詰めると唯一絶対神に至る。これを「世界はそうなっている」といって押し付けてくるのが西洋である。
「違う」は感覚世界に由来する。身体のことである。個性とは身体のことである。本来言語はこの「同じ」と「違う」を結びつける役割のものである。
日本の思想(がないという思想)は自然という実体を基礎に置いている。これが身体に対する暗黙の確信を維持している。そうであるがゆえに、今多くの人が揺らいでいる。そして自分探しに出る若者が多いのも納得できる。
自分が変わることである。身体に基礎を置くことである。
2.著者について
昭和十二年生まれ。東京大学名誉教授。『バカの壁』がベストセラーになったのは2003年。本書は400万部売れ、題名はそのまま新語・流行語大賞の特別賞まで受賞している。
養老先生が医者にはならず解剖の道へ進んだのは、生きた人間を診ることが不安で仕方がなかったからだという。
数あるご著書を拝読するに、一貫して脳化社会について語っておられ、都市と脳化との関係をベースに人が思考に頼りすぎることが何をもたらすかについて、現代社会のみならず古代文明についても言及しながら警笛を鳴らし、最後に自分はもう年寄りだから知らん、とあたたかく突き放してくれている。
母一人子一人の母子家庭で育った方で、早くに他界(先生が4歳の時)された父親の記憶は朧であるそうだ。母親は小児科医で、夫の面影を先生に見ていた節があると受け止めていて、それがゆえに先生は人の愛情に対してある意味冷淡なところがあると述べている。ただ、戦後国家レベルで極貧の時代を過ごしたにもかかわらず、大学まで行くことができているというのは、同世代の方の話を聞く限り相対的には恵まれていたのかもしれない。
『バカの壁』は何でもかんでも言葉で伝わるものではないだろう、ということだが、それを言葉を使って説明するのは、角度を変え、分野を変え、定義を変え、いくつもの趣向を凝らして語る必要があると思う。この本に限らず養老先生の著書の内容はどれもが多岐に渡る知識を有機的に融合させ、それを平易な言葉に置き直して語りかけている。最近は遺言だの半分死んでるだの、なんだかそういう準備でもしてるのかと思うような題名が使われているが、まだまだ著作を読みたい一人である。
3.気づき
発見と題しているが、新しく見つけた、というのではなく、無思想と考えた方がわかりやすいし、それを推奨するという意味での掲題だ。
ともすればメディアから流れてくる情報にあおられがちな私たちに対して、様々な角度からアンチテーゼを投げかけ、個性とは体のことだと明言し、日々流れてくる情報に惑わされず、自分の体と相談して生きろと言っておられる。
先生の本がこれだけ売れるのは、世の中の言葉を使って、学問体系になっていないいくつもの領域をつなげ、意識無意識と言った明らかに心理学的な表現と論理をも見事に組み込んで、私たちが抱える諸課題の構成について解説してくれているからだろう。
先にも述べたが、養老先生の本は多岐の分野にわたる知識をもって著されているため、あっちへ行ったかと思えばこっちの話になって、でもそれが面白くて追っているうちに提言された結論に納得してしまうというところがある。ある種のフットワークを要求される本をずっと書いておられるのだから、先生の頭の体力(?)は年齢とは関係なく鋭敏なんでしょうね。
要約をご覧になってお分かりの通り、凡人の頭では切り貼り羅列的な説明に堕してしまっていることは認める。しかし、先生は言葉を変え、表現を変えながら一貫してメッセージを発信されている。それは、正しい考えが先にあってそれに人間(の体と命)をあわせるのではなく、より多くの人々が自分の人生の主人公となって生きるためにどんな思想が大切か、思想というものをどう受け止め、構築したらよいか、ということではないだろうか。時代を経るほどに、この「生きる」の手前に様々な形容詞を求めるようになった。豊かに、健康に、幸せに、安心して、リッチに、安全に、成功者として、などなどなど。そういうものを当たり前にもとめられるようになったということもできるけど、一方で私たちはいつも迷っているようにも思える。ちょうど江戸末期、お伊勢参りがはやったころの庶民の心持に似た部分があったように思えるが、これはいくつもの願望(もっとお金があれば、もっと健康であれば、もっと仕事があれば、もっと平和であれば・・・)を実現してきた末に、「あれ、それで私は幸せになったのか」という根本的な疑義が国中に蔓延しているように思える。それに対して、つい疎かになりがちな私たちの心と体・命のつながりの部分にきちんと目を向けること、そこなくして願望を達成したところで土台が揺らいでしまっている、そんなふうに拝読するのはおかしいだろうか。
本作品『無思想の発見』は、表題、内容とも特に心理的な観点から取り上げたかったものであるが、先生の他の著書を読まれている方はお分かりの通り、都市化された脳化社会に対する対処方法を説いておられるという意味ではどれも同様の結論に至っている。不安やそれによって生じるおかしな出来事は、本来自然であるはずの私たちが、ああすればこうなる的な生活空間で暮らすようになった結果であり、べき論から外れた無意識や体、虫、そういったものが意味するところまでを含めて世界が構成されていることを今一度思い起こす必要がある、そう言っておられるように思える。
最後に、養老先生のような本の分野を何というのかわからない。だが、どの分野化を問わず多くが好んで読まれる方の本というのは、読者、自分が所属する地域の人々に対する愛情が行間ににじみ出ているように思う。ドラッカー氏、コルク氏、日下氏、前野氏など、これから少しずつ取り上げていきたいが、類似の感性を感じる。
4.おすすめ
世に心理系の本は五万とあるが、その多くは類似の用語と論理をもって解説されている。それほどに一個の確立した領域であり、それにより自分を取り戻す人々がいるのは素晴らしいことだが、そこから外れてしまった人々がいるのもまた事実だ。養老先生の本はそういった既存の心理の本とは一線を画したカウンセリング的な側面を有している。ここで提案したいのは、先生の著書をセラピーの一つの指標とすることだ。
幸福感と安心感をもって生き、ワクワクを追い求め、それがお金と豊かさとを連れてくるという一連の流れを説く流行りの(?)自己獲得物語は個人的には嫌いではないが、おそらくその根っこに必要な安定感を獲得するための指標としてはいささか不十分であると思う。そこには、体という領域が明示的な意味において抜けているためである。
先生の本を読むとお金持ちになります、はまずない。だが、幸せとか健康とかを突き詰めていくとこういうところは外してはいけないのではないだろうか。
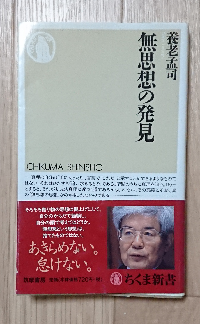

最近のコメント